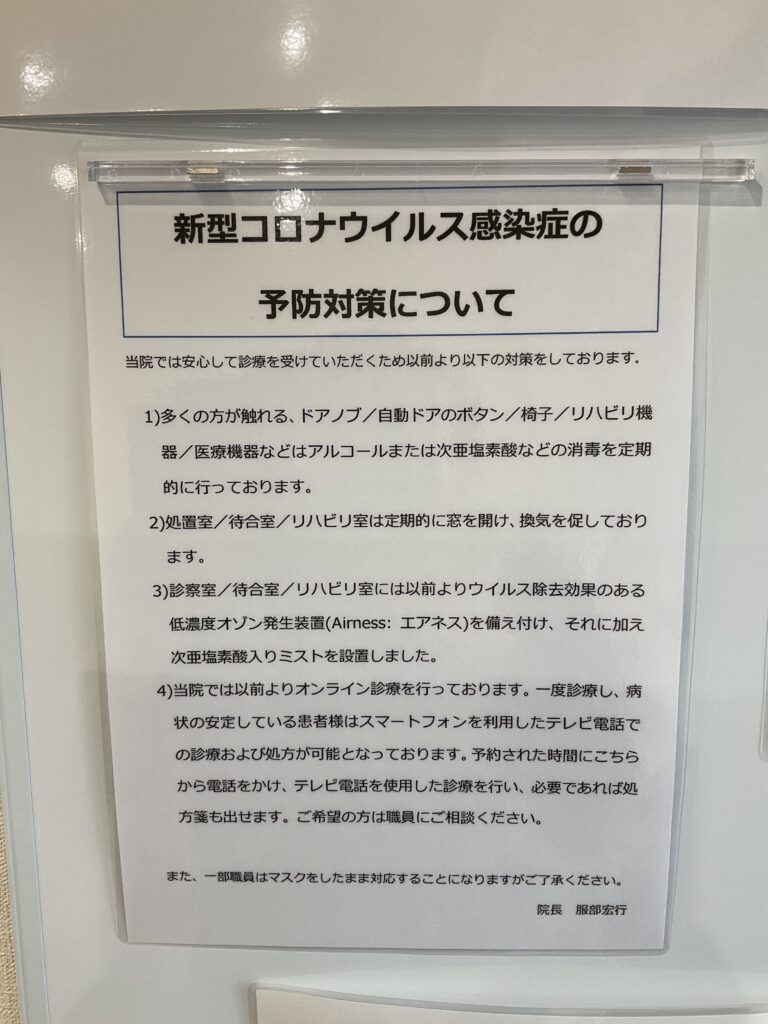痛みへの対処法
2022年02月25日
こんにちは!
2月も後半に差し掛かりますが、まだまだ寒い日が続いています。
その影響か、最近治療中によく『痛みに対しては温めた方がいいの?冷やした方がいいの?』と質問を頂くことが多くなった気がします。
そこで今回は『冷やした方が良い痛み』と『温めた方が良い痛み』についてお話をさせて頂きます!
注意
:悪性腫瘍、血圧異常、心疾患、皮膚疾患、重篤な循環器障害、感覚異常、出血傾向のある部位
以上に当てはまる方は今回のセルケアで症状が悪化する可能性があります。
○冷やした方が良いケース
ケガをしてから約72時間(3日)までは急性期と呼ばれ、組織の炎症を抑えることが最優先されます。
また、元々痛みがあった箇所の痛みが増強し熱をもってきた場合なども冷やす事で炎症を抑える効果が期待できます。
1.患部が熱をもっている
2.腫れている
3.赤くなっている
上記の3つは代表的な炎症所見です。1つでも当てはまるならアイシングを行ってください!
〈方法〉
『水で濡らしたタオル』や『氷水が入った袋』などで1-2時間の間隔をあけて、約20分行います。
※温度が冷たすぎるもので長時間冷やし続けると凍傷のリスクがあるので注意してください!
○温めた方が良いケース
慢性的な痛みは原則として温めた方が良いとされています。
その際には、必ず痛みが出現している箇所が腫れていたり熱を持っていないかを確認してください。温めることにより、症状が憎悪する可能性があります。
温める事で血管拡張、筋肉の緊張緩和、代謝亢進、浮腫軽減、リラックス作用などといった効果が期待できます!
〈方法〉
①蒸しタオル
タオルを濡らし軽く絞り電子レンジで加熱。(500wで1分)
熱が逃げないように袋に入れて密封し、20分を目安に温めます。

②入浴
40℃程のぬるめのお湯に浸かる事で、血行が良くなり疲労回復や筋肉の緊張緩和が期待できます。肩まで浸かってしまうと水圧による心臓への負担が大きくなるため、みぞおち程度の高さでの入浴がおすすめです!
以上が『冷やした方が良い痛み』と『温めた方が良い痛み』の説明となります!
どちらを行えば良いか分からない方はお気軽に受診、相談に来てください!